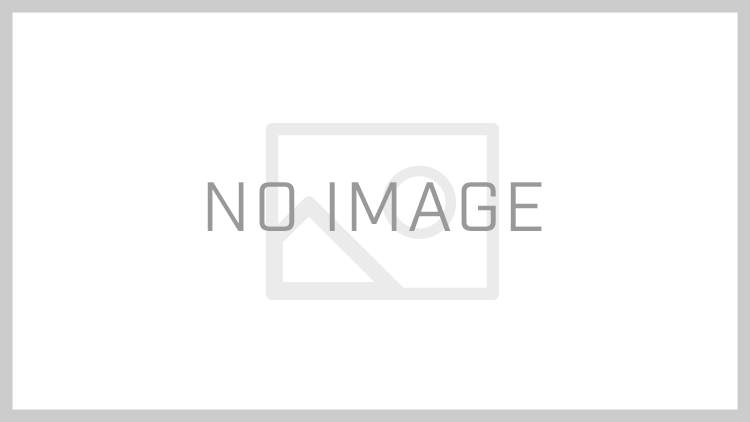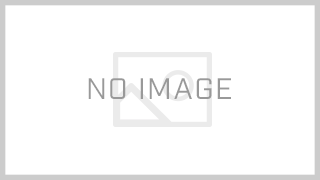子どもと家族を支える福祉について
大塚 晃
はじめに
障害者施策に関する法律
発達障害者支援法(平成17年4月1日施行)
障害者自立支援法(平成18年4月1日施行)
→現在は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)として施行されている。(平成25年4月1日一部施行)
*この文章は、障害者総合支援法施行前に書かれた論文であるため、原文では障害者自 立支援法となっている。現在の内容に大きな違いがない場合、そのままの記載とする。
論文の視点
「子どもと家族を支える福祉」について考えてみたい
子どもと家族を支える福祉とは何だろうか
1.障害者自立支援法などの法律によって提供される福祉サービス
福祉サービスだけで障害者の生活を成り立つわけではないが、重要なもの。
→障害者を支える福祉サービスが全国どこにおいても十分利用できるものとなっていない状況においては、福祉サービスを含めた支援体制の整備は課題。
2.障害者が理解される地域社会の存在
障害者の安心して暮らすことのできる地域社会の実現を考えるときの前提
→地域における共生社会の実現をより確かなものにするためには、子どもの頃から、障害の有無にかかわらず、共に遊び・学び・暮らす環境を整えていくことが重要である。
今まで提供されてきた福祉サービスへの反省
反省・・・障害そのものに焦点が当てられ、治療や教育が必要であり、専門家による専 門家が支援しやすい環境で提供されてきた。
そうではなく・・・障害のある子どもは”障害のある子ども以前に、子どもである”
発達障害のある子どもへの福祉サービス
障害者自立支援法は、身体障害・知的障害・精神障害の三障害種別を超えてサービスを一元的に提供するものであるが、そこに発達障害という言葉はない。
*障害者自立支援法における「障害者」とは、
身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者(肢体・視覚・聴覚・内部など)
知的障害福祉法にいう知的障害者
精神保健福祉法第5条に規定する精神障害者(発達障害者を含み、知的障害者を除く)
すなわち、発達障害者は、精神障害者の中に入ってくる。(実際は?)
*障害者総合支援法のにおける「障害者」とは、
上記三障害+難病患者
発達障害を法律に明確に位置づけると共に、福祉サービスが発達障害者に適合したものとして提供され、全国どこの地域においても実際に利用できることが課題
→現時点では運用に任されている
福祉サービスにおける質の高いサービス提供とは
障害者が、施設に入ってどの代梨園を受けるか決めるのではなく、どのような事業を 利用して豊かな地域生活を送るかということに転換。
→施設完結ではない。
メリット:自由な生活を送ることができる
デメリット:自分で「決めなけれ」ばならない。 (論点1)
どの地域においても提供されるだけでなく、利用者個々のニーズにあった質の高いサ ービスが提供されることが重要。
→個別支援計画の作成
参考資料http://www.pref.tochigi.lg.jp/e05/welfare/shougaisha/sesaku/documents/13purosesu.pdf
エビデンスに基づく支援は、福祉分野における化学的方法論の確立のための挑戦
今後の子どもと家族を支える福祉を考える
4つのポイント
(1)子どもの将来の自立を見据えた発達支援
障害の早期発見
障害を持つ子どものサービスへの関係づけ
現事業の整理
「子ども発達支援センター(仮称)」の設置
(2)障害のある子ども本人のみならず家族を含めたトータルな支援
家族の支援を含めた「子育て」の支援(受容から子育てへの視点転換)
(3)子どものライフステージに応じた一貫した支援
医療・保健・福祉・教育及び労働などの連携
→特に移行期(引き継ぎが不十分など)に困難 (論点2)
(4)身近な地域における支援
身近=サービスの実施主体と行政の実施主体
サービスの実施主体・・・基幹的な組織を機能させる
行政の実施主体・・・・・都道府県と市町村の権限整理
おわりに
障害のある子どもの支援を新たに再構築する絶好のチャンス
「配慮された子育て」の必要性
→子どもの自立に向けた発達支援と家族支援を一体的に提供することで、地域社会 における共生の実現が可能となる。
論点1 地域で自立生活を送るためには、全て自分で決めなければならない。重度知的障 害などがある人にとって果たしてそれがよいのか?
(一般的には脱施設と言われ、入所施設から地域へと言われているが。)
論点2 問題とされている「引き継ぎの困難さ」について、各立場(医師・教師・福祉従事者・ボランティアなど)でなぜ困難さを極めているか、どのようにすればスムーズに進めていくことができるのか。